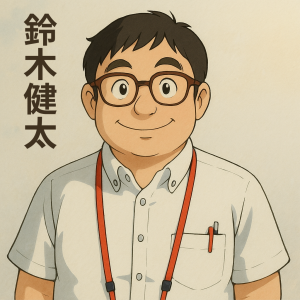こんにちは。鈴木です。
不思議なことに、最近あちらこちらで同じような話を聞きます。
大河ドラマ「べらぼう」では、のちの滝沢馬琴が絵師の喜多川歌麿に対して、「お主…、男色(なんしょく。つまり、男好き)ではないのか?」と尋ねるシーンがありました。歌麿は、「俺は男も女も好きさ」と答えます。その後、歌麿は「俺はそもそも男か女かで人を分けたりしねえんだよ。俺は『好きな人』と『それ以外』で分けてるもんでさ」と、世間の物差しで自分は人を見ていない、ということを馬琴に伝えました。
一方、朝ドラの「ばけばけ」では、のちの小泉八雲が島根県の松江に到着した際、主人公の松野トキと握手をするシーンがありました。
「あの時、先生の手が震えちょったんです。異国から来て、初めての場所に来て、初めての人たちに会って、その人たちがみんな期待しちょる。きっとあの時から怖くて…、日がたてばたつほど怖くなって、イライラして、怒って、むちゃ言って…。ジゴクジゴクと叫んだりして…。ヘブン先生(小泉八雲)も人間です。私たちと同じ…。天狗でも、鬼でも、河童でもなく」
このあとの、天岩戸の話に繋がるあたりが、もうたまらなかったです(笑)。
そして、西田千太郎がモデルとなっている吉沢亮さん演じる錦織友一が、「私も、人間扱いしていなかった。震えていたなんてこれっぽっちも気付かんかった。ありがとう。恩に着る」とトキに頭を下げる場面もよかったですね。
さらに先日、ほぼ満席状態の映画館で「もののけ姫」を鑑賞しました。
アシタカの(腕の)、エボシに対する怒りがたかまり、今にも斬らんとするシーンで、ハンセン病患者が、「お若いかた、わたしも呪われた身ゆえ、あなたの怒りや悲しみはよくわかる。わかるが、どうかその人を殺さないでおくれ。その人はわしらを人として扱ってくださった、たったひとりの人だ。わしらの病をおそれず、わしのくさった肉を洗い布を巻いてくれた。生きることはまことに苦しくつらい…。世を呪い、人を呪い、それでも生きたい…。どうか愚かなわしにめんじて…」と言います。
宮崎駿監督は、「この映画は子ども向きではない」という周りからの声に対して、「この映画を一番深いところで理解しているのが、10歳くらいの子どもたち」と話していたようです。
男、女、外国人、病人、大人、子どもなど、カテゴライズの弊害が、ときに人の眼を曇らせます。アシタカの言う、「曇りなき眼(まなこ)で物事を見定める」ことが、今の時代こそ必要なのかもしれません。
作品は違えど、あらゆる人が同じようなことを物語に織り込んでいました。それらがまるで意図されているかのように自分の耳に聴こえてくる。不思議な経験でした。