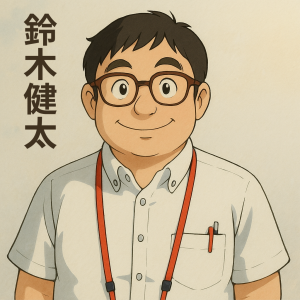こんにちは。鈴木です。
本日より、公立中学校で定期テストが始まりました。明日以降または来週実施の学校もあるかと思いますが、いずれにしても中3生にとっては内申点を上げる最後のチャンスであり、気が気でないと思われます。
今回は、中1・中2生に向けて、来年の今頃までにどういったことが問題となるか、今のうちに知っておいてほしいことを記しておきます。
〈現中2生は、内申点を上げる機会はあと3回〉
例えば、現在の内申点が32とする。目標内申点が42だとすると、あと10上げなければならない。すると、1回あたりどのくらい内申点を上げたらよいのかがわかるはず。成績を改めて見て、何の教科が上げやすいかを確認。内申点が5以外の教科で、観点評価にAが1つでもある教科は狙い目。主要5教科は定期テストの出来にも左右されやすいから、まずは副教科をあげ切っておくのもいい。今回の場合だと、1回あたり3か4、内申点を上げねばならないから、9教科中5、6教科にアプローチできるといいだろう。3上げたいから3教科攻めるのでは、リスクが高い。だから、必ず多めに攻める。行いがよければ、予想よりも多くの内申点を頂けるかもしれない。
ところで、中1生の子はチャンスがあと5回ある。だからといって、安心してはいけない。上げられるのは今のうち。きっと、多くの中3生はそう思っている。そして、多くの現中1生も、中3生になったら同じことを思ってしまうことだろう。皮肉だが、それくらい、上手くやれる子は少ないのだ。少数派になれるかどうかは、あなたの心がけ次第。行動し始めよう。
〈学力調査は入試に向けたよい訓練となる〉
こう言ってはなんだが、定期テストは所詮範囲が狭い。だから、実は点数が取りやすい。一方で、学力調査は定期テストよりも範囲が広く、学年が上がるごとに範囲は公立入試に近いものとなっていく。これを利用しない手はない。定期テストでは点が取れるけれど、学力調査では点が取れないなんてのは論外。何度も言うが、定期テストは範囲が狭いから、しっかりと対策をすれば高得点は十分に狙える。また、「内申点に関わらないから、学力調査の対策はやる必要がない」とか言っている子は、重要度がわかっていないだけだから、相手にしなくていい。範囲が広いテストはなかなかないのだから、ありがたく学力調査を利用させてもらおう。
〈学習リズムを築けるかどうかが人生を決める〉
大袈裟なタイトルだが、事実だからしょうがない。今年早稲田大学に合格した静高生が言っていたことがある。「結局のところ、よい大学に行っているのは、日常の小テストで毎回満点か1ミス2ミスの高得点を取っている人たちですね。自分は数ヶ月、中だるみの時期があったので、それが全てを決めたように思います」と。これは、私が「後輩たちに何か一言」とお願いしたときに彼が言ってくれたことなんだけど、元々は東京大学を目指していたから、早稲田大学に行くことになって心底悔しかったんだと思う。そんな彼が言ってくれた金言。この記事を読んでくれた子が生かしてくれたら幸いだ。
明倫館でも、毎日の学習習慣がある子はできる子が多い。オンライン保護者会でも伝えたことだけど、コツコツ勉強できる人が強いのは間違いない。継続は力なり。これは、やり続けた人にしかわからないだろうね。
〈量をこなした人にしか見えない世界がある〉
落語に、剣術の修行を積んだ人物が、相手の構えを見ただけでどのくらいの強者であるかを見抜けるようになる話がある。勉強も同じで、ある量までこなして初めてわかるようになる領域がある。そこまでくると、これまで苦労して学んできたことが嘘のように楽しめたり、充実感を抱けたりするようになる。明倫館でも、これまでに何人もの先輩が同じような境地になり、少し前までには手の届かないと思われていた志望校に果敢に挑み、合格を果たしている。彼らに共通しているのは、中1・中2のときの彼らと中3のときの彼らとでは、まるで別人のように変わっているということだ。だからこそ、中1・中2のときには「まず無理だね」と思われた志望校に合格できたんだよね。嘘みたいな話だと思うだろうけど、実際に何人もの例があるものだから、誰だって同じようになれるかもしれない、と信じて止まなくなるんだよね。ここでは書ききれない先輩たちのエピソード、興味があったらお話するから、ぜひ尋ねてみてね。聞けば君も「同じようになれるかもしれない」と勇気がもてるはず。いつの時代も、前例を築いた先人たちは偉大な存在だね。