明倫館塾長ブログをご覧頂き誠にありがとうございます。明倫館塾長の永倉です。
中学生になると、勉強は「やらされるもの」から「自分で進めるもの」へと変わっていきます。とはいえ、多くの生徒はまだその切り替えがうまくできません。塾で教えていても、『言われたことはやるけれど、自分からは動けない』という子がとても多いのが現実です。では、どうすれば中学生が自立して学べるようになるのでしょうか…。答えは、特別な才能でも、強い意志でもありません。毎日の生活の中に自分で学ぶ小さな習慣を積み上げることに尽きます。
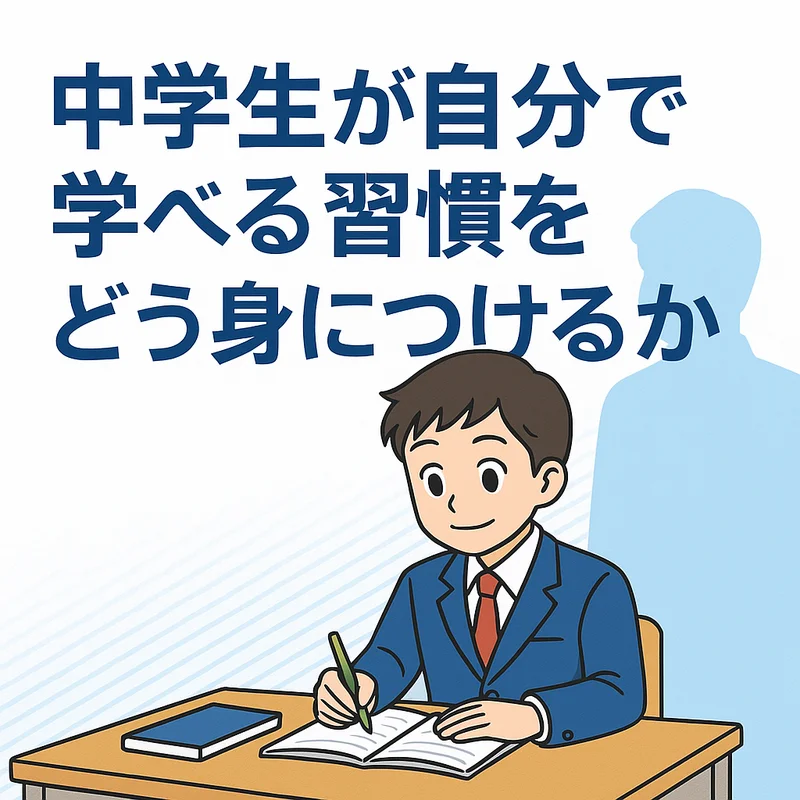
■自立学習の第一歩は「自分で決める」経験から
まず必要なのは、勉強の中に小さくてもいいので 、自分で決める 要素 を入れることです。例えば…、『今日の勉強の最初の10分は自分で選んだ科目』『宿題の中でどれからやるかは自分で決める』『日曜日だけは自分で作った学習リスト』で進める。たったこれだけでも、子どもは驚くほど変わります。自分で選んだことに責任を持てるようになるからです。
■小さな成功体験が習慣化のカギ
自立学習を妨げているのは「できない不安」や「勉強への苦手意識」です。これを乗り越えるには、小さな成功体験を積み重ねることが必須です。
例えば、『5ページだけ予習したら授業が分かりやすくなった』『10問だけ自分で復習したらテストの点が少し上がった』『塾のワークをコツコツ進めたら、提出物に困らなくなった』など、こうした『できた』の積み重ねが、子どもを自然に自立へと向かわせるのです。
■家庭でできるサポートは「管理」ではなく「応援」
保護者の方に意識してほしいのは、過干渉にならないことです。「ちゃんとやったの?」「早く机に向かって」この声かけは一見良さそうに見えて、実は、勉強を親の仕事”に変えてしまいます。サポートの正解は、『結果より取り組みをほめる』『勉強を始めたら邪魔しない』『スケジュールを親が作るのではなく、一緒に相談する』このスタンスが、子どもに自分でやる理由を育てます。
■塾が担うべき役割は「やり方の提供」と「継続の仕組み」
塾は、ただ教える場所ではありません。自立学習を育てるためには、次の2つが欠かせません。①効率的な学び方を教えること:どんな順番で進めると成果が出るのか、どこでつまづきやすいのか。プロだからこそ示せる正しい努力のルートがあります。②継続できる仕組みを作ること:チェックテストの習慣、ワーク進捗管理、個別アドバイス。続けられる環境があるから、子どもは行動を維持できます。塾と家庭が同じ方向を向けたとき、子どもの成長は一気に加速します。
■自分で学べる力は、一生もの
自立学習は中学生だけの話ではありません。高校、大学、そして社会に出てからも必要な、大切な力です。だからこそ、中学生の今こそが習慣づくりの黄金期です。毎日の小さな積み重ねが、未来の大きな自信に変わります。親と塾が無理なく支え、子どもが自分の力で前に進めるように、その一歩を一緒に作っていきたいと思います。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
明倫館
塾長 永倉秀樹
TEL:054-204-3911(明倫館本部教室)
click↓




